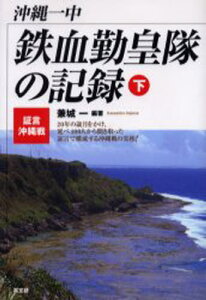沖縄県立第一中学校の学徒は上級生は一中鉄血勤皇隊に、低学年は一中通信隊に編成された。
生徒 動員 273人 戦死者 153人
教師 動員 12人 戦死者 6人
第三小隊壕は生徒や職員が掘った3カ所の小隊壕の一つで、各壕とも数十人が入っていたとみられる。生徒たちは各部隊に分散配置される1945年5月14日ごろまで、これらを拠点にし敵の動向を見張る監視や壕掘り、弾薬・食料運搬などの任務に当たった。一中の勤皇隊は沖縄戦に約220人が動員され、約150人が死亡したとされるが、詳細は不明。
琉球新報『戦禍を掘る』 一中鉄血勤皇隊

砲音の中 卒業式 生徒たちも不安と緊張
艦砲は遠く方で不気味な音を響かせ、途絶える気配はなかった。日没とともに、養秀寮中庭に集まって来た生徒たちの数は100人近くになっていた。前夜、卒業式のあることを友人から知らされた当時県立一中4年生の比嘉重智さん(56)も、その中にいた。
前年、「緊急学徒勤労動員方策要綱」の決定によって、5年の修業年限が1年短縮され、昭和20年3月27日のこの夜、卒業式を迎えた。地を伝わって響いて来る砲音は、卒業式という厳かな儀式を迎える生徒たちに、さらに緊張を強いていた。
5年前の創立60周年を記念して建てられた寄宿舎の養秀寮。中庭の一段高い土手で、藤野憲夫校長ら教職員が寮を背にして並んでいた。そこには来賓の島田叡知事、第5砲兵隊司令部の砂野芳人中佐の顔もあった。
向かい合うように4、5年生が整列。“ひな壇”との間に1個のランプがほのかに揺れていた。その明かりが米艦船のいる方向にもれるのを防ぐため、5年生数人がまわりに立っていることが、いやが応でも“戦場”であることを痛感させた。
ほのかな明かりだったが恩師や学友の表情が険しくなっているのを知るのには十分な明るさだった。
式の直前だったか、その最中だったかは、さだかでない。遠くの方で鳴っていた艦砲が突然、式場の近くに落ちた。ドッドーン。とどろく砲音。「逃げろ!」と思った瞬間、式場で大きな怒鳴り声が響いた。「動くな! 動いてはいかん」。配属将校の篠原保司中尉の声だった。
「あれは見事と言うよりほかない。“ひな壇”も生徒らも動揺、動こうとした時に、間髪を入れずの一喝に知事はじめだれも動けなくなった。式の終わるまで2、3発至近弾があったように思うが、だれ一人として動く者はいなかった」
泰然自若としているように思えた篠原教官だったが、やはり緊張していた。砂野中佐を紹介する時、「これから砂野“中尉”殿の訓示がある」と勘違い、しかも最後まで気づかなかったから訂正されることもなかった。
藤野校長はじめ多くの人が演壇に立ったが、比嘉さんの記憶にある言葉は少ない。たった一つ、島田知事が「この卒業式こそ日本一の卒業式だ」と言う言葉に感激した。(もっとも、どの学校の卒業式でも言っていることを戦後知り、がっかりもしたが…)
◇ ◇
比嘉さんが県立一中に入学したのは昭和16年。時代の影は顕著に学園に表れて来た。「1年の時に“富川清事件”、3年には『先輩の軍神・大舛大尉に続け』だった」と比嘉さんは振り返る。
“富川清事件”は、一中で秀才の名を高めた富川清さんが、第一高等学校と陸軍士官学校を合格、選択の末、一高への進学を決めた。これに配属将校が怒り、教練検定を取り消し、新聞でも取り上げられるなど、個人の将来にまで軍人が支配、また新聞も世論づくりに一役買う時代になっていた。
「入学時の胡屋朝賞校長は大正デモクラシーの影響もまだ残って自由な雰囲気。17年7月に藤野校長が赴任して来たが、戦闘帽で登校、軍国主義教育も厳しくなった」
そして18年、ガダルカナルで戦死した一中―陸士出身の大舛松市大尉に、軍人最高の個人感状が贈られると、「大舛大尉に続け」と熱狂的になる。田端一村教諭が取材、小野重朗教諭が執筆、「大舛大尉伝」が沖縄新報に連載もされた。
18年、波上祭も中止になった。「女学生らと接触できる数少ない機会だったから、その中止を聞いた時は、ひじょうにがっかりした」と、比嘉さんは今でも残念そうな表情で話す。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月12日掲載
修業年限を短縮 レコードではかない抵抗
19年、「緊急学徒勤労動員方策要綱」に基づいて比嘉重智さんらの修業年限が短縮される。「新聞を読んだ父親から聞かされた時はショックだった。あと2年間遊べると思ったが、1年しかない。そのあとは兵隊かと思うと、つまらなくなった」
比嘉さんら4年生と5年生の対立があったのは、その年の新学期が始まって間もなくのことだ。4年生が5年生に呼び出され、当時中学では“恒例”の鉄拳制裁を浴びたことに端を発した。「卒業は一緒ではないか。同等の権利を与えよ」が主張だった。
4年生全員が3日間の授業ボイコット。「私は“付和雷同”組ではあったが、趣旨には大いに賛成だった」。毎朝、テニスコートそばの土手に集まった。校長が呼んでも一致団結して応じない。
こうした強硬策が功を奏したのか要求は聞き入れられる。「最上級生を経験して社会に出るのと、そうでないのは大変な違い。同時卒業を配慮したのか、甲飛、予科練などへの進学で5年生が減少、勢力数を考慮しての学校側の判断だったのかは分からない。しかし、要求が通ったからといって、すぐに同等になれるものでもなかった。昔の1級先輩というのは大変な違いがあったから―」と話す。
授業はほとんどなく、飛行場設営や陣地構築作業が日課となっていく。戦局の悪化は明らかだった。
サイパンが陥落してあとの夏、比嘉さんは県立工業学校の校庭で、32軍の渡辺正夫軍司令官の話を聞いたことがある。一中、工業、師範、青年学校の生徒や、首里市民を前にしての訓示だった。
司令官は声をふりしぼるように訴えた。「軍民ますます一致協力、敵にあたらねばならぬ」と言い、「敵の沖縄上陸は必至。その時には全県民、軍と運命をともにし、玉砕する覚悟を決めてもらいたい」と絶叫に近い口調だった。机をたたき、涙して訴える姿に驚いた。そしてまた、軍の最高首脳の口から「敗北」を意識した言葉が出てきたことに、それまで連戦連勝を信じていた比嘉さんは驚かされた。
思いもかけぬ修業年限の短縮で、残された学生生活は1年間。限られた時間を有意義に使おうと、比嘉さんが没頭したのはレコード鑑賞だった。もちろん流行歌ばかりをかけた。「はかない青春のレジスタンス」と比嘉さんは言う。「支那の夜」「旅の夜風」「湖畔の宿」「満州娘」「ああそれなのに」「蘇州夜曲」…手に入るだけのレコードを集められるだけ集めた。
同級生の親友、桑江健さんが熱心だった。毎日のように比嘉さんの家にやって来る。どういうわけかレコードを次から次に集めてくる。黒砂糖を手に蓄音機から流れて来る音に、知らぬ大人の世界への憧(あこが)れもまじって陶酔した。
20年1月に、首里3カの学生会「三星会」の分散会が比嘉さんの家で開かれた。だれかが泡盛も持っている。自然とにぎやかになった。当然、蓄音機からは流行歌が流れていた。
比嘉さんの家の近くには部隊が駐留、歩哨が立っていた。その歩哨の軍靴の音が、比嘉さんの家に近づいて来る。カツ、カツ、カツ…。「怒鳴られる」とみんなが思った。だが、靴音はヘイの外で止まり、入ることはなかった。じっと音楽に耳を傾けている。「内地を思い出して歩哨任務中、音楽につられて来たのでしょう」。決戦への緊張が強まる中、だれもがやすらぎを求めているころだった。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月13日掲載
激しくなる空襲 女学生は看護隊員へ
首里崎山町の比嘉重智さんの家が、20年2月ごろから、県立二中通信隊の宿舎になった。近くの首里崎山教会に通い、通信教育を受けていた。「3年生18人ほどだったと思う。家はチャーギ作りだったので、二中生たちがくぎを打とうとしているのを父親があわてて、やめさせたことをおぼえている」。
“ライバル”二中の通信隊員に、いい部屋を占拠された比嘉さんは、奥の6畳間が生活の場になった。
その日も比嘉さんはレコードに耳を傾けていた。その時、ふと思いついたのが各中学の校歌を収めたレコードだった。一中の校歌が終わってあと蓄音機から二中の校歌が流れた。「彼らがどんな反応をするだろうと流してみた」。
背にした戸の陰で人の気配がする。そして、10センチ…30センチ……50センチ―ゆっくりと戸が開けられ、5、6人の生徒たちが部屋に入って来た。だが、すぐに二中の校歌は終わった。それとともに二中生らも、バツの割るそうな顔をして引き揚げていった。比嘉さんは「私が一中で、しかも1期先輩。当時は話のできる状態ではなかった」と苦笑しながら言う。
父・重真さんが防衛隊に召集されていったのは2月28日だ。数日前から気配は察していたが、父親は息子に召集を告げることはなかった。
その日は小雨の降る朝だった。持病の薬を抱えて父親は「じゃ行くよ」と言う。比嘉さんは「行くのか」とだけしか言えなかった。息子の前に召集令状を差し出す父親。比嘉さんは、そこに書かれている部隊番号「山四二八四」だけを頭の中にたたき込もうと、じっと見入っていたが、父親はすぐにしまい込んだ。
沖縄戦の始まった3月23日、空襲がやんだころから比嘉さんは親友の桑江健さんらと、マチマーイ(街回り)に出る。目的は女学生の姿を見ることができないかということだった。だが、すでに看護要員として多くの女学生はかり出されていた。
民家の雨戸も閉ざされていたが、そこに新聞紙に墨書きされたポスターが張られている。兵隊らが書いたのだろうか。こう書かれていた。「沖縄よいとこ一度はおいで 米英撃滅したところ」。空襲後の静かな街。一方がめくれたポスターが風にパタパタ揺れているのが、ものさびしげに思えたと言う。
やがて艦砲も激しくなって日中は壕から出ることもなく、遠雷のように聞こえる砲音と、時折ズシーンと響く振動に耐えなければならなかった。そして迎えたのが3月27日の卒業式だった。
◇ ◇
卒業式は、至近弾が時折落ちる中で行われたが、配属将校の篠原中尉の一喝が効いたのか、その後は逃げ出そうとする者もなく無事に終わった。終了後、篠原中尉は卒業生に向かって「鉄血勤皇隊」を編成することを告げる。
全員に住所、氏名、学年、血液型を書いて出すように命じた。卒業生を送るため駆けつけてきた下級生の中にも希望して出す者がいたが、篠原教官に怒鳴り返された。
その晩、首里近郊にいる者は家族の元へ、それ以外は養秀寮に残された。
母親はこの日、特別に卵の入ったタマナー・チャンプルー(キャベツいため)を作って待っていてくれた。比嘉さんは「明日からは学校と一緒に行動するから」とだけ告げた。母親は、多く聞くこともせず、ただうなずくだけだった。
母と息子は黙ったままで食事を続ける。比嘉さんには「これが最後かもしれない」という思いが走った。1カ月前に夫を送り出し、今また一人息子を送らねばならぬ母親の心情を思うと多く語る気もしなかった。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月14日掲載
階級の違い実感 初めて軍服着てはしゃぐ
翌3月28日、養秀寮に集まった4、5年生の数は前日を上回っていた。軍服一式が支給される。ゲートルだけは「自分のを使え」と言う。
夏冬、4年間を1着で通した制服は、つぎはぎだらけでボロボロになっていたから、何の未練もなかった。だが1本の白線と校章のついた戦闘帽を捨てるにはためらいがあった。「私服は一切持つな」と強く言われていたので、戦争が終わってから取りに来ればいいと近くに埋めた。
篠原保司教官は隊の名称を「鉄血勤皇隊一中隊」と告げた。そして班の編制。第1小隊32人、第2小隊28人、第3小隊33人。このほか県庁に19人が配属され、炊事班に約10人がいた。比嘉重智さんは第2小隊だった。この日、第5砲兵隊司令部(球9700)から訓練、教育のため渡辺見習士官ら8人が派遣されている。
軍服には星が一つ。さらに胸には鉄血勤皇隊を示す「菊水」のマークがつけられていた(菊水のマークは後日取りはずされた)。
その夜、養秀寮に宿泊した学生らは、初めて着た軍服がうれしくてはしゃいでいた。だが、中学生気分が抜けず、多くが腰に手ぬぐいをぶら下げている。「チャーガ(どうだ)」「チャーガ」と自分のかっこ良さに浮かれていた。その時、部屋に兵隊が入って来たのも気づかなかった。
「キサマら上官に敬礼もしないのか」と、そこにいた2、3人にビンタが飛んだ。
「ちょっと前まで一緒に壕掘りもしたし、私たちがフィータイグヮー(下級兵)とあなどっていた階級。それが軍服に着替えた途端、星一つの違いをはっきり知らされた。うかつにも上官が天皇陛下の分身であるなど注意されるまで気がつかなかった」
4月4日ごろから14日ごろまでにかけて生徒たちの遺書が集められる。「私は8、9日ごろに書いたように思う」と比嘉さん。
砲爆撃が激しくなり、壕生活になっていたそのころは、艦砲のやんだ夕方、外に出て雑談するのが楽しみになっていた。そこで遺書を学校側から書くように告げられる。「遺書の受け取り人の生死さえ確実でないのに書いてもムダではないか」と比嘉さんは思い、渡されたザラ紙を手にしばらくあぜんとしていた。
やがて、たそがれが闇に移る。時間にせかされるように一気に書いた。
「父上様母上様 十有六年間育てられた御両親様とも別れる時が参りました 私が戦死したと聞いても決してお嘆き下さいますな 一人子として何ら恩に報いることができず死ぬことを残念に思っています(4行判読不明)自分は分只感謝で一杯です 父母の恩がしみじみと感じられます」
このあと「祖父母様にも…」と続けた時、多くの顔が浮かび、涙があふれ出た。
比嘉さんは「『国のため』『靖国神社に』と建前は書かなかった」と言うが、残された遺書には書き込まれていた。「自分も死ぬ時には立派に御国の華と散ります 重智が死んだと聞いたら微笑んで下さい」。苦笑しながら比嘉さんは「16歳の私たちの骨の髄まで国家主義の教育がしみ込んでいたんですね」と言う。
遺書とともにツメと髪の毛も封筒に入れられた。ツメは歯で食いちぎる。連日の作業で土の入ったツメはかむとシャリ、シャリと音が出た。丸刈りの2センチほど伸びた髪は、額のはえぎわから一つまみし、ハサミで切った。
「死んだあと受け取る人はいるのか」―まだ疑問だった。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月15日掲載
初の戦死者出る 敗北つぶやく篠原教官
戦時中に動員された県内21校の学徒隊のうち、学校として遺書を書かせたのは一中学徒隊だけとされる。生き残った一中元学徒らの証言などによると、外地での戦争経験を経て同学徒隊本部に配属された将校と、当時の藤野憲夫校長がよく口論していたという。太田副会長は「当時の一中学校関係者は、これが勝ち目のない戦争であり、死を覚悟しなければならない時だと冷静に判断したのでは」と推測する。
「もう一度、顔がみたくてたまらない」 沖縄戦動員の元学徒、別れを惜しむ心をつづる 修復遺書を那覇で展示 | 沖縄タイムス
鉄血勤皇隊一中隊から初の戦死者が出たのは4月4日ごろだ。養秀寮が全焼、その中から2人の勤皇隊員の焼死体が出てきた。3月30日には危険だということで、3小隊に分かれて壕に移っていたのだが、息苦しい壕生活にたまりかねて、この夜2人の生徒は無断で寮に宿泊していたという。
明け方、比嘉重智さんらのいる第2小隊壕に、生徒らが告げに来た。篠原保司教官が飛び出して行ったが、ついて行こうとする生徒はいなかった。「自分が助かると思う者はいないし、今さら死体を見てもしようがないという、あきらめの気持ちがあった」と比嘉さんは言う。
2人の遺体は、篠原教官が毛布にくるみ、寮東側の空き地に埋葬した。10センチ角ほどの二つの墓標は戦後十数年も残っていた。
このころから、配属将校の篠原教官に変化が出る。第2小隊壕で、教師や生徒らを前に、財布を取り出して紙幣を燃やしはじめた。「この戦争は勝てない。この戦争は負けだよ」とつぶやきながら―。
「必勝」を信じきっている者たちの前で、「敗北」を口にした初めての発言だったから、たちまち生徒たちに広まった。
南方戦線で敗北を体験したことのある軍隊体験者は生徒たちを引率する立場にあって、情勢を冷静に見、そして正直に発言した。「それはまた、“軍国主義者”である校長に対しての抵抗でもあったと思うのです」と比嘉さんは振り返る。
一中の鉄血勤皇隊の中で特徴的なことは、29人の生徒たちが、篠原教官によって次々に除隊させられていることだ。
卒業式の晩、まず3人が「翌日からは来なくていい」と親元に帰されたのに始まり、「健康」などを理由にして除隊させている。比嘉さんが、その中で最も強く印象に残っているのが、4月26日、親友の桑江健さんら7人が除隊になった時のことだ。
その日の朝、全員が集められ、7人の除隊が告げられた。上空には米軍の観測機が飛んでいたが、篠原教官は「動くな。動くと発見されやすい」と命じ、全員ビクビクしながら整列させられていた。
全員の前には7人の生徒が並んでいる。7人を見ながら篠原教官は「勤皇隊員として、国のため、滅私奉公したいかもしれないが、健康を損なっており、残念ながら除隊させざるを得ない」と言った。
比嘉さんは親友の桑江さんの顔を見た。口を真一文字にして悔しそうな顔をしている。だが、比嘉さんには無理して表情をつくっているように見えた。「こっちがうらやましいと思った分、どうしてもうれしさをこらえているように映った」
「家族の元に帰りたいか」と何人かに尋ね、「はい」と答えた3人を除隊させた5月14日まで、29人を篠原教官は勤皇隊から去らせた。
篠原教官は、どこから探して来たのか、壕内に蓄音機を持ち込み、レコードを聴くことが多くなってきた。もちろん流行歌だ。その中には比嘉さんが好きだった「春よいずこ」という流行歌も入っていた。
哀愁をおびたタンゴ調の歌だった。戦争で青春もなく、やるせない気持ちしかなかった比嘉さんが、最も気に入っていた歌だった。
篠原教官がどんな気持ちで聴いていたのか比嘉さんは知ることができなかった。この美男の配属将校は、6月4日、喜屋武で迫撃砲の破片をこめかみに受け戦死した。一時休憩中の木陰で静かに眠るように亡くなったという。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月18日掲載
雑炊だけの夕食後のひととき、先生方が希望的観測をまじえて勝ちいくさの話をしていた。そこに篠原教官が真顔で「こうなったら戦争はもう負けです」といった。ブーゲンビル島で米軍と戦った配属将校の発言だけに、まわりの先生方はしゅんとなった。それまで聞き役だった藤野校長は、きっとした表情で「沖縄で負けることは絶対にない。これから連合艦隊も出動してくるだろうし、援軍も逆上陸するはずだ。戦いはこれからが正念場だ。軍人のあなたがそんなことを言ってどうするんですか。あなたは配属将校ですぞ」とたしなめた。
しかし、教官は、「戦争はもう負けです」とくり返した。それに対し校長も、「絶対に負けていない。何を根拠にそう言うのですか」と反論した。「われわれは壕にじっとしているだけで、外に出られるような状態ではない。これでは戦争に勝てるわけがありません。こういうのは負けいくさです」と声は低いが、はっきりした語調の篠原教官の声が、その場にたまたま居合わせたぼくの耳に聞こえた。だまって二人の話を聞いている先生方の前で、藤野校長は教官を叱咤していた。《兼城一『沖縄一中鉄血勤皇隊の記録(上) 』高文研) p. 269》
戦況悪化で一線へ 5月14日境に師弟分散
4月12日は雲一つない日本晴れだった。珍しく艦砲も遠くの方にしか落ちないし、飛行機も飛んで来ない。
その日、比嘉重智さんの第2小隊壕に、防衛隊へ召集された父親が訪ねて来た。2人は壕を出て、20メートル程離れた大きな木の下まで歩き、腰掛けた。父親が口を開いた。「ナンジヤミ(つらくないか)」と尋ねる。比嘉さんはだまって頭を振った。
それからの10分間ほど、2人はほとんど無言だった。40歳を過ぎてから防衛隊に駆り出された父親の苦労は、目の前の姿を見れば十分に察せられた。また一人息子を見る父の目にも、少年にとって過酷な生活が続いていることは容易に察せられたはずだ。
40年前の光景だが、比嘉さんには、まだなまなましく焼き付いている。話の途中、突然黙り込んでしまった。顔を上に向けたが、それでも涙はこぼれ落ちた。「生きて帰っていれば冷静に話せるのだが、どこで死んだのかも…」―タオルで拭いながら言い、また黙り込んだ。
◇ ◇
一中の校舎が崩れ落ちたのは4月20日だ。「この日午後五時頃、那覇港沖の米艦隊からの砲撃の一発が沖縄一中の校舎に命中した。大地をゆるがす轟音で勤皇隊の壕もゆさぶられた。校舎の2階の窓からは猛烈な火が吹き出し、夕暮れの空を焦がした。生徒たちは呆然となって校舎の前に立ちつくした。六十年の伝統を誇った学びの舎はあえぎながら助けを求めるようにして崩れ落ちた」(「養秀百年」から)
比嘉さんは、その前日、教員2人とともに講堂に行っている。床板をはがして壕内で使用するためだ。すでにその時から攻撃を受けていた。何によるものか講堂の木の枠組の窓が燃えている。
コンクリート造りの講堂の中を軍靴で歩くと、その音が響いて来る。窓枠は燃えている。比嘉さんは戦争映画の主人公のような気分になり、妙に興奮した。
だが、2人の教師はそれどころではない。はがそうとした床板も取りやすいところから3分の1はなくなっている。残っているものは道具を使わなければ取ることができない。それでも比嘉さんらは素手で挑戦していたが、2人の教師は「もう危ない。帰ろう」とせかした。
講堂には、尚温王の筆といわれる「海邦養秀」のへん額が掲げられていた。2人の教師は「あれをどうしましょうか」「国宝級なのだが…」と話をしていたが、結局、そのままにした。
◇ ◇
5月に入ると、日本軍の前線は崩れ始め、首里付近にも危機が迫って来た。
5月12日のことだ。鉄血勤皇隊の第2小隊壕に、沢岻方面から下って来た少尉が部下とともに入って来た。「お前ら出ろ!」と言う。近くにいた教師は「ここは鉄血勤皇隊の壕であります」と説明したが、「キンノー隊?。それは何だ。とにかく、この壕は我々が使う」と言う。“壕追い出し”だ。
その時、配属将校の篠原保司教官が出て来た。教官は中尉である。「キサマ、少尉のくせに何だ」と言うなり往復ビンタを幾度も浴びせた。少尉らは黙って壕を出て行った。
戦況の悪化は、一中の鉄血勤皇隊を“戦力”として必要としてきた。結成以来、師弟がともに行動してきたが、5月14日を境に分散することになる。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月19日掲載
野戦重砲隊に配属 担架の将校を放り出す
藤野憲夫校長の訓示が長く感じられる。砲弾は遠くの方に落ちているが、照明弾は近くで上がっている。時折、首里城に向かっている砲弾なのか、頭上をヒュルヒュルという音を残していった。
野戦重砲第1連隊に配属になった27人の生徒を前に藤野校長の訓示は続いた。「戦局は時々刻々、か烈を極め、戦いは必ずしもわれに利あらず、勤皇隊も統一行動は至難となった」―緊迫感を与えるはずの「時々刻々」の言葉も、校長の口ぐせだったから、ここでは生徒たちの軽い笑い声を呼んだ。
「日ごろ鍛えし、一中健児の意気と…」「最後の勝利は皇国日本にあり…」「勝利は最後の5分間にあるを信じ、天は鴻(こう)毛よりも軽く…」と訴え、「諸君の敢闘と武運を祈る」と訓示を閉じた。
5月14日の夜、養秀寮北側の第3小隊壕前。遠くに落ちていた砲弾が気のせいか、だんだん近づいて来るように感じられた比嘉重智さんは「長すぎる。早く終わってくれ」と祈るように訓示を聞いていた。
しかし訓示が終わり、「カシラー、ナカッ」の号令で校長の顔をながめた時、「これが最後かもしれない」と思い、小さな特徴まで刻みこむように見つめていた。
各部隊への配属先が決まったのはこの日昼だ。前々日に県庁に配属されていた19人も帰隊、これらも含めて新たに配属された。比嘉さんの記憶するところによれば、勤皇隊本部約20人、第5砲兵司令部約10人、野戦重砲第1連隊27人、独立重砲第100大隊約20人、独立測地第1中隊約12人、独立工兵第66大隊約20人となっている。首里での戦死者6人、除隊者は29人だ。
野戦重砲第1連隊に配属された比嘉さんはがっかりした。「“ヤジュウ隊”と聞いた瞬間、大砲を担がされるような響きで、悪いとこに行かされると思った。それに比べて、“ソクチ(測地)隊”の響きのよさ。うらやましくて仕方がなかった」
比嘉さんがうらやましがった測地隊の12人は、だれ一人生還した者はいない。砲兵の倍委、測地隊も最も一線に近く配置され、味方の着弾地点を確認、報告する任務を負っている。地上での活動が中心だから危険度も高い。比嘉さんは、そのことを知らなかった。
野重隊の27人は校長訓辞のあと、早速、引き取りに来ていた兵隊らとともに、東風平村志多泊の野戦重砲第1連隊医務室第6中隊に連れて行かれる。
途中、同部隊の負傷した将校1人を4人1組となって、担架でかつがされたから、その道程は果てしなく遠いように思えた。部隊配属が決まった時、鉄かぶと、帯剣、38式教練銃などを手渡された。その時、たった15発の弾を受け取ると重くて前のめりになるほど、体力が弱りきっていた。銃は他の生徒に持たしたが、将校の体重は4分の1とはいえ、肩からぐいぐい食い込んできた。
担架の上の将校は、ずっと文句の言いっ放しだった。「痛い、痛い」を連発するが、担いでいる生徒自体、体力もないうえ、ぬかるみに足を取られるから仕方がない。南風原を過ぎたあたりでは艦砲が近くに落ちてきた。たまらず担架を放り出して身を伏せたら、負傷した将校は傾斜を転がっていった。
艦砲がやんで再び担架をかつぐと、「オレを投げ出したのはだれだ」と、わめいていたが、だれも返事しようとする者などない。疲れ切って、そんなことなど、どうでもいいように思えていた。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月20日掲載
砲弾の中の伝令 親友母子と永遠の別れ
野重1連隊の医務室壕は東風平村志多泊にあった。北側をながめれば首里の方にNHKの受信塔が建っている。「あの付近には、まだ両親らが残っているはずだ」と比嘉重智さんは感傷的にもなった。
だが、そんな思いはすぐに去る。首里に比べれば、艦砲なども散発的にしか落ちず静かだ。勤皇隊のための寝床も2段か3段のベッドが準備されている。しずくが毛布をぬらすのには閉口したが、壕生活にはあまり不満はなかった。
壕の前を流れる小川のせせらぎは平和な光景そのものだった。戦争は外の世界のことのように思えた。
志多泊に到着した日の翌日、5月15日と比嘉さんは記憶する。
「識名宮を知っている者はいないか」―大きな声で下士官が勤皇隊員に呼びかける。「識名宮」―そこは子どものころから昆虫採集にもよく行った。先祖の墓も近くにある。ウシーミー(清明祭)などのたびにも通った。
楽しかったころの思い出が重なり、勢いよく「ハイッ」と手を挙げた。だが、すぐに「しまった」と思う。周囲を見ると同僚らは一様に安どの色を見せていた。比嘉さんは戦争のことなど忘れていた。しかも、その付近は弾着の激しいところだ。もう遅かった。
識名宮付近にある司令部までの伝令が任務だった。下士官と比嘉さん、そしてもう1人“貧乏くじ”を引いた勤皇隊員の3人。
識名宮に近づくにつれ、砲撃は激しくなり、識名園付近では集中的な砲撃で一歩も身動きができない。伏せながら、初めて「来るんじゃなかった」と思った。砲撃がやんでからも大変だった。識名宮の森を目標として来たのだが、すでに森は消えている。立ち往生している比嘉さんに、「何だお前は知らないのに連れて来たのか」と下士官はなじった。
手を挙げたばかりに付近の壕を、砲弾の中、1人で回って探さねばならないハメになってしまった。
勤皇隊員は翌日からも交代で伝令に行くのが任務だった。比嘉さんが次に司令部へ行ったのが5月27日。この日、司令部が撤退したので、志多泊での最初と最後の伝令は比嘉さんが務めたことになる。
その時には、首里の戦線も崩れる寸前、敗色を一層濃くしている。途中、両足のない兵を見た。両手を支えにして、尻を引きずるように進んだのだろう。尻のあたりから泥んこの道に50センチぐらい、柔らかい大便が一筋流れていた。翌朝、帰る時に見たら、筋は3メートルほどに延びていた。
一日橋を越え、識名の坂にさしかかった時だ。「シゲトシーヤアラニ(重智ではないか)」と声をかける者がいた。聞きおぼえのあるその声は、親友の桑江健さんの母親だ。見ると桑江さんもそばにいる。母子は南部へ避難する途中だった。
容赦ない砲撃は相変わらずだった。近くにも落ちる。「早くしろ」と上等兵に促されるまでの立ち話は30秒ぐらいだったかもしれない。レコードを聴き、酒を飲み、奪われた青春を何とか埋めようと遊び回った親友。一方は坂を上り、一方は坂を下る。「おれたちの壕を頼って行け」と比嘉さんが言うと、「チューサ チューサ カンナジ チューサ(行くよ。必ず行くよ)」と笑顔を見せて答えていた。比嘉さんが聞いた親友の最期の言葉だった。志多泊の壕を訪ねた形跡はない。母子は、その1カ月後、南山城跡付近で亡くなったと聞いたのは戦後だ。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月21日掲載
初めて女学生に遭遇 乏しくなる一方の食料
識名の本部壕を撤退する時、識名の南側斜面は負傷兵が無数に倒れていた。その間をぬうように比嘉重智さんらは進んだ。
比嘉さんらのズボンは何度か引っ張られた。まだ元気のいい者は上着の袖まで引っ張る。「オレたちも連れて行ってくれ」―か細い声で哀願するが、そんな余裕などない。とっさに「あとから衛生兵が来ますから」と振り切って進んだが、「貴様らもそんなことを言うのか」と言い、あきらめてか握った手の力が抜けていった。
志多泊の壕にも負傷兵は少なくなかった。比嘉さんらは、そこの医務室で手術して切り取った手足を捨てに行くのも仕事の一つだった。壕の前を流れる小川まで行かねばならなかったが、体力が日に日に衰えていた比嘉さんらは、途中、壕から死角になるくぼみに放り出していた。
6月1日、負傷兵5、6人を乗せ、トラックで新城の分院に運んだことがある。トラックで行くのはありがたかったが、道という道は砲弾で大きな穴があいている。ちょっと進んでは穴に落ち立ち往生という始末だ。
そのトラックを追うようにりゅう弾砲が、ぬかるみの道にポコッポコッと落ちて来たから気が気でなかった。とうとうトラックがぬかるみにはまってしまった。勤皇隊員が押し、やっとのことで動き出したと思ったら至近弾。思わず全員が近くに伏せた。「痛い、馬鹿!何してんだ」とわれに返ったら、負傷兵の上に伏せている。「弾からかばおうと思いました」と弁解したが、バツが悪かった。
トラックから分院に運ぶのが、また大変だった。中腹にある壕入り口はかなりの傾斜だった。担架で担ぐ苦労を知らない負傷兵は、「しっかりしろ」と口だけは達者だった。やっと運んだ時はぐったり、壕入り口で休んでいたが、中に入って行った下士官が伝えた言葉は全身から力が抜けていった。「負傷兵は志多泊まで連れて帰る」。負傷兵を運んだのは、野重1連隊の撤退に備えてのものだったが、分院もまた撤退準備中。「われわれも撤退するのに何でここに運び込むんだ」と怒鳴られたという。
来た道を再び引き返す。坂道を担架で背負い、艦砲の穴に落ちたトラックを押しながら―。
ただ、比嘉さんが今だに胸の高鳴りを感じることが、その時にあった。分院の壕で初めて女学生を見た。二高女生が2人、かいがいしく負傷兵の手当てをしている。まわりの衛生兵らは、女学生らに勤皇隊員が来たことを「おい、中学生が来たぞ。お前らの友だちが来たぞ」とひやかしている。
そんな声を女学生らは聞き流すように、ただ黙々と手当てを続けていた。ツンとしていて勤皇隊員を無視しているようだった。だが、手にしたガーゼは負傷兵の同じところを何度も往復していた。
6月2日に志多泊の壕を撤退、翌4日未明に比嘉さんは真壁に到着する。休む間もなく、来たばかりの志多泊への伝令という“貧乏くじ”。体力は限界に近いほど消もうしていた。
壕を出て3、40メートルほど歩いたら、りゅうさん弾が襲って来た。その時、比嘉さんは伏せたまま動けなくなってしまった。別に傷を受けたわけでもないが立てない。一緒にいた上等兵はせかすが、体がいうことをきかない。上等兵は比嘉さんのそばまでやって来て、「おい行こう」と言うなり、わき腹をしたたかにけった。「コンチクショウ」と思ったら、すぐに立てた。「近くまで寄って来た時、『しっかりせよと抱き起こし』の歌のイメージでいたものが予想外の一撃。どういうわけで立てたのか今でもわからに」と比嘉さんは言う。
その日、伝令から帰った時、雑のうに入れてあったカツオブシがなくなっていた。食料は日に乏しくなっていた。
(「戦禍を掘る」取材班)
死んだ女性に化粧 恐怖の急造爆雷を担ぐ
比嘉重智さんらの部隊にも辻の女性たち数人が、看護婦としてかいがいしく働いていた。その中の1人が死んだのは、真壁まで撤退した6月上旬のことだ。
比嘉さんが壕入り口を通った時、女性たちが泣きながら死に化粧をしてあげている。「○○ちゃん、きれいよ」と。もの言わぬ仲間に語りかけている。死んだ女性の顔が、間からチラッと見えた時、比嘉さんはハッとした。薄く塗られたおしろいに、ほおの紅がうっすらと浮かんでいる。「人形のようにきれいだった」。戦前にも見たこともない美しさだった。
真壁に移ってから将校らが外に出ることは、ますますなくなってきた。小便するのも飯ごうですまし、比嘉さんら勤皇隊員が捨てに行く。その飯ごうをまた負傷兵が奪い取ろうとする。「おれにも水を飲ませろ」。「小便です」と答えても信じず、飯ごうをつかんだ手を振り切るようにして進まねばならなかった。背にはありったけのばり雑言が浴びせられた。
そのころ、「赤いハンカチと手鏡を持ち、陰毛をそった女性があれば通報すること」との伝達があった。それはスパイだと言う。まじめな顔で、そんなことが将校の口から出るようになっていた。
艦砲の合間に外に出て雑談するという勤皇隊員の楽しみは、まだ続いていた。むしろ慣れるに従い、艦砲再開のギリギリまで楽しむようになっていた。比嘉さんは壕に戻るのが遅れ、死ぬ思いをしたことがある。
途中に迫撃砲の集中砲火―。くぼ地に身を隠し、親指で目、残り4本で耳を押さえたままじっとしていた。5分、10分と時間はたつがやむ気配はない。背中に触れるようにピューピュー弾が飛ぶ。たまらず目を開けたら赤い火の玉が体をかすめるように飛んでいた。恐怖のあまり、駆け出したい衝動にかられたが、やっとの思いで抑えた。
そんなことが多かったから勤皇隊の係の上等兵は、壕口で「早く入れ」「早く入れ」と促すのが日課。上等兵は負傷、戦死したが、脳症になってまで「勤皇隊は無事か」とのうわごとを繰り返していたという。
6月19日、24日の勤皇隊員は3分隊に編成され、斬(き)り込みに出る。解散命令があったのか前夜のうちに壕内を埋めていた負傷兵は消えていた。
比嘉さんらの分隊は7人編成。急造爆雷が1個準備されていたが、だれも持つ者などいない。浦崎という1等兵が断を下した。「比嘉、お前持て」。168センチの身長が判断材料だった。
「仕方なく担いだが、担いだ途端、頭がスーッとし重さも感じなかった。死を超越した“無我の境地”というものかもしれない」。ただ涙だけはあふれ出して困った。月夜の晩だったから下級生に見られるのが恥ずかしく、横を向いて涙をぬぐった。
◇ ◇
「急造爆雷」は沖縄戦で数多く使われた。32軍の高級参謀・八原博通氏の手記「沖縄決戦」には次のように経緯を書いている。「(略)最期に大本営陸軍部参謀次長後宮将軍からじかに必勝戦法を承った。(略)貧乏人が金持ちと同じ戦法で戦えば、負けるに決まっている。そこで日本軍には『新案特許』の対戦車戦法が発案された。それは十キロの黄色薬を入れた急造爆雷を抱えて、敵戦車に体当たりして爆破するのだ。(略)もちろん、この必死攻撃に任ずる兵士は直ちに三階級特進させるのだ(略)」
現実に爆薬を背負わされたのは学生たちが多かった。3階級特進の話もほとんど聞かれない。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月26日掲載
恐怖の米軍勧告 恐怖の急造爆雷を担ぐ
敵陣を突破して活路を開くはずだった斬り込みも、予想をはるかに超える米軍の警戒で断念する。しばらく進むと至近弾が数発、銃火器の集中攻撃もある。ただ伏せてやむのを待つよりほかなかった。
急造爆雷を背負わされた瞬間から、比嘉重智さんは死への恐怖がすっかり消えていた。だが、みんなは違う。強行突破という気違いじみた行動を選択しなかった。といって、すぐに退却できるわけではない。斬り込みの命令を受けた者が、元の壕に引き返すのは、勇気が必要だった。
夜明け前、ようやく壕に引き返すことになった。比嘉さんは背負っていた急造爆雷を、途中で捨てた。
「怒鳴られて、また斬り込みに行かされる」―そう思って壕に入ったが、意外なことに壕に残っていた軍医中尉も主計中尉も歓迎してくれた。比嘉さんらとは別に南の方へ行った二つの分隊は壕に帰って来ることはなかった(比嘉さんが戦後分かったところでは、戦死、行方不明者は6人となっている)。
薄暗い壕生活に再び戻った時、比嘉さんは驚いた。壕に残っている者の多くは将校だったが、食料がまだ豊富にある。牛肉の缶詰もあり、炊事するのに固型燃料が使われた。勤皇隊員が炊事しごちそうはみんなに振る舞われたが、比嘉さんは食べることができなかった。疲労こんぱいして胃袋が受け付けなくなっていた。
戦闘が始まって3カ月、勤皇隊員の心はすさんでいた。学生のころの純心な気持ちは、軍隊とともに行動するうち、間断ない砲弾で吹き飛ばされた。
6月21日ごろだ。壕に子ども2人を連れた60代ぐらいの老女が逃げ込んできた。「一緒にいた人たちは捕虜になった」と助けをこうように入って来たがみんなの目は冷ややかだった。勤皇隊員の口から「この壕から出て行け」との言葉も出た。「自分だけが助かりたいという気持ちになっていた。私たちもすでに加害者になっていた」と比嘉さんは振り返る。
壕入り口の方から「デテコイ」「デテコイ」の声が聞こえたのは23日だ。前日、水汲みに行った防衛隊員が米軍が近くにいるのに驚き、あわてて壕に戻った際、石油缶をけ飛ばし、察知されていた。黄リン弾が投げ込まれた。
勤皇隊員は拾った防毒面で防いだが、その防衛隊員は防毒面もなく、せき込んでいた。その時も勤皇隊員から「クルサリンドー」とおどす声が飛んだのを比嘉さんは記憶している。
米軍の投降勧告に壕内は騒然となった。比嘉さんも血の気が引いた。「戦闘準備」で弾を込めようとしたが銃はさびついている。「もう最後だ」。足がガクガク震えた。ごぼう剣をノドに当ててみたが、痛くて自決などできない。
そのうち英語のできる者が米兵と話し、「殺さない」ことを確認して投降した。約30人。壕を最後に出た兵は「イシカド中尉が自決しました」と報告した。その少し前、銃声があった。
久しぶりに見た昼の光景は真っ白だった。草も木も海も―、白を基調にした世界だった。壕の近くに黒く牛のように膨れあがった死体が3体あった。移動できず、衛生兵の手で“処置”された重傷患者だった。死体に群がるハエが何かの拍子に離れ、勢いよう飛び回った時、比嘉さんはわれに返った。
◇ ◇
「中国で戦った兵が沖縄戦で『こんなのは戦争でない』と言っていたが、狂気の世界だ。私たちもいつの間にか精神状態が異常になっていた。戦争はいつも弱い者が損するようになっている」と比嘉さんは言う。
(「戦禍を掘る」取材班)1985年3月27日掲載
沖縄戦から五年後の一中学舎。
米国陸軍通信隊: Destruction to an old school building in Shuri City, which was caused by Navy and Artillery shelling during the battle for Okinawa. 沖縄戦で海軍と砲兵隊の砲撃で破壊された沖縄県立第一中学校校舎 首里 1950年 3月30日
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- 比嘉 重智さん|証言|NHK 戦争証言アーカイブス
- 学徒兵の遺影 ブラジルから里帰り – QAB NEWS Headline
- 65年前のきょうは1945年9月30日(日) – QAB NEWS Headline