海野福寿・権丙卓『恨(ハン)―朝鮮人軍夫の沖縄戦』河出書房新社 (1987)
毎年、
終戦の日になると、日本の各局が戦争を扱う番組を制作する。しかし誰も不思議に思わないのだろうか。被害としての太平洋戦争を語るのみで、加害としての太平洋戦争を扱う番組は圧倒的に少ない。語られない、その記憶の「沈黙」に光を当てる番組も少ない。証言者は存在する、にも関わらず、だ。
こうして見えない存在となった「記憶」は、いつの間にか無かったことにされていく。もし、そのまま声が聞かれなかったならば。
戦争の記憶は、むしろ「語られていない」(unspeakable) 部分にこそ光を当てる必要がある。
貴重な一次資料の記録の書。
《 海野福寿・権丙卓『恨(ハン)―朝鮮人軍夫の沖縄戦』河出書房新社 (1987) 》
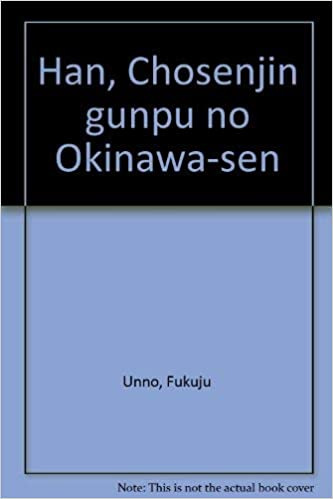
「まえがき」から
一歴史学徒として太平洋戦争史研究をみてもそう思う。四〇万とも、五〇万ともいわれる多数の朝鮮人を軍人・軍属として動員したにもかかわらず、その実態をほとんど明らかにしていないからである。太平洋戦争史関係書のどれをひもといてみても、落丁のように朝鮮人軍人・軍属の記述は欠落している。
研究書・体験記の豊富な沖縄戦についても事情は同じで、何万人といたはずの朝鮮人は端役としても登場しない。わずかに一九七二年調査の『第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団報告書』(尾崎陸団長)の沖縄での聴き取りなどがある程度。阿嘉島・慶留間島・座間味島・渡嘉敷島などの慶良間諸島の場合も、そこが沖縄戦最初の米軍上陸地点であることもあって書かれたものが少なくないが、住民集団自決に話題を奪われ、数百人に上る朝鮮人軍夫の影は薄い。太平洋戦争史の研究が精密化すればするほど、その空白が目立つ。一方、被害者である韓国側にも民衆の姿をとらえた研究書や体験記は無きにひとしい。「日帝」、「日帝三六年」という言葉は日常語として使われているし、植民地体験が人びとの歴史意識にどっかり腰を据えているが、その極にあった戦争体験を受難者の立場から被害の実態を通じて明らかにしようとはしない。…
阿嘉島・岳原展望台で「処刑」地を探す沈 在彦さん (1986年11月19日)。
「キム・サンギリー、シム・ヂェオニワッター」(金相吉やーい、沈在彦が来たぞー) 「キム・サンギリー、シム・ヂェオニワッター」
一九八六年一一月一九日、四一年ぶりに沖縄・阿嘉島を再訪し、島の中央、岳原展望台に立った 「太平洋同志会」招魂団の一人沈在彦さんは、声をふるわせて亡友の名をくり返し叫んだ。 「太平洋同志会」―一九四四年「国民徴用令」によって徴発され、「軍夫」という名の軍務雑役労働者(軍属)として沖縄へ送りこまれた、韓国・慶尚北道慶山郡出身者の生き残り二百数十人が、一 九四六年二月、米軍の捕虜として収容されていた米軍の収容所(屋慶名?)で結成した旧友会である。
寄る年波にはかてず、一人欠け、二人欠けて現在の会員数は七、八〇人。生あるうちにもう一度沖 縄を訪れ、万斛の恨みをのんで死んだ同僚の魂を故郷に連れ戻そう、という彼らの宿願が沖縄大学の協力によって実現したのである。招魂団は沈在彦さんのほか千沢基(「太平洋同志会」会長)さん、金潤台さん、申晩祚さん、鄭実寛さんと権丙卓教授。
招魂団一行が山に登ったのは、日本軍によって殺された朝鮮人軍夫七人の「処刑」地跡を探すため 7だった。それは山頂付近にあった戦隊本部のちかくと思われた。金相吉氏も「処刑」された一人である。
沈在彦(シン・ジェオン)さん証言
… この時になって日本人は傲慢で冷酷な本性をむき出しに示しました。
本部の洞窟に食料がまったくないというなら話は別です。しかし、われわれが運んだり、集めたりした食料だけでも全員が当分は食っていける分量はあるはずなのに、彼らは、われわれを虐待しながら食べ物をほとんどくれませんでした。その上、夜になると部落の周辺とか米軍の集積所へ行って物資を探してこい、と命じました。それは、すぐ死に繋がる危険が伴う仕事でしたけど、同僚たちはむしろ喜んでそれを受けたものです。というのは、その機会に外の様子を知ることもできたし、米軍に手を上げて脱走するチャンスを求めることができると思ったからです。
食糧の搬入などの労働を担った朝鮮人軍夫は、どれぐらいの食糧がどのように本土から運び込まれたかを一番よく知る立場にあったことは他の証言にもある。例えば金元栄 (1992)。
そのせいか、日ごとに同僚の数は減っていきました。帰ってこない人が死んだのか、捕虜になったのかは分りませんでしたが、人数が少なくなればなるほど兵隊の監視、監督は強化されたのです。われわれの不満はつのり、一日も早く戦いの結末がつくよう願っていましたし、米軍が早く進撃してこないのを恨んだ人さえいました。
いつの間にか、われわれの間には新しい隠語が作られました。「菓子を食いに行かないか」というのです。食べ物を探しに行き、米軍が落とした菓子を食べたことがある同僚の話から生まれたのですが、それは、脱走して捕虜にならないか、ということを意味していたのです。
軍夫の数は次第に少なくなり、そう、八○人とは残っていなかった。依然、昼は塹壕・洞窟掘り、夜は掘った土を運び出す作業がつづけられたけれど、坑はいっこうに大きくなりません。兵隊たちはいらいらして、厳しく督励しました。毎日のように雨が降り、洞窟内は湿気で蒸し暑いうえ、大きな蚊がわれわれを悩ませました。だにと蚤もわき、脱いだ服をはたくとボロボロしたに落ちるほどでした。
ひとつ、明らかになった事実があります。それは、韓国と日本とを一人対一人で比較してみると、われわれの民族の方がはるかに強いということです。困難なことが増えていく状況の下で、この優劣ははっきりしてきました。彼らは乏しい物資をわれわれには差別的に少量しか与えず、虐待したけれど、不安にかられて落ち着きを失っていたのは、むしろ日本人でした。
われわれはどこかへ行って、何かを探して食べたのです。うまごやしなどの雑草、海藻、ソテッの茎、アダンの実、木の芽、木の皮など。蛇やヤシガニを追い、ヤドカリを拾いました。生のものは海水で塩漬けにして食べ、名も知らない野草は味をみて磁極性の強いものを避けましたが、それでも間違えて中毒したり浮腫んだりしたものです。とにかく、危機を克服する粘り強い底力は、日本人とは比べられないほど韓国人にはありました。でも、山と野には採って食べられる草も木も見えなくなってしまいました。
ひと月ほどたった四月下旬のある日、山を下り、ポケットにさつまいもをしのばせて戻って来た同僚が日本兵に摘発された。それまでにも住民の畑作物を掠めた者、食料収集を命ぜられ帰隊時間内に戻らなかった者などがいて、それら「犯罪者」七人が呼び出されました。金相吉(安心面槐田洞)、千有亀(河陽面大谷洞)、許乗昌(河陽面釜湖洞)、黄末社(安心面東内洞)ら(他の三人は慶山郡以外の出身者)です。
軍律会議が開かれたかどうかは、立ち会った軍夫同僚がいないので分らないけれど、七人は銃殺刑線をいい渡されたのです。多分、戦線を離脱し、軍紀(住民の食料盗奪禁止)を乱した、というのがその理由なのでしょう。うしろ手に縛られ引き立てられて行く七人の後に、墓穴掘りを命ぜられた七人の軍夫がついて行きました。私もその一人。
山腹の展望哨から三○○一四○○メートル下った草むらに、深さ三○センチくらいに掘った穴の前に立たされた七人に対し、指揮者の兵隊が訊いたのです。「最期に言いたいことはないか」「われわれは腹が減っていた。それなのに君たちは食料をくれなかったではないか。われわれは働くのはいい。どんなに働かされても我慢しよう。仕事なのだから。しかし、働けるだけの食料もくれずにただこき使ったのだ。われわれは心から君たちを恨む。腹が減っていたのだ」
年長の千有亀が昂然といったのです。刑死を目前にしていい放つ、その凄絶な言葉に兵隊たちは一瞬ひるんだ様子でしたが、「朝鮮人は死ぬまでメシか」と、憎々しげに侮蔑に満ちた悪態をつくと、生いもを取り出して千有亀の口に押しこんだのです。目隠しをされ、谷間に向って立たされた七人の背に向けて撃たれた七発の銃声。のけぞって倒れる者、墓穴に転げ落ちる者、一発で死に切れず、とどめの二発目、三発目を撃ちこまれて絶命した者もいました。
銃殺隊が引き揚げたあと、私たちは同僚の遺体に土をかけたのですが、死んだと思った許兼昌が「俺は死んでいない」というので軽く土をかけ偽装しました。
後日、捕虜収容所で再会して分ったことですが、右肩を撃ち抜かれた彼は、夜を待って墓穴から脱出、谷を下り山をこえて海岸に出、米軍に助けられたのだそうです。九死に一生をえたわけですが、帰国優の一人六〇年、韓国戦争(朝鮮動乱)に做され、両脚凍傷で翌年亡くなりました。
罪もない同僚たちがこのように殺されるのを見守っただけでなく、墓まで掘らされた私たちの屈辱。帰り道は行く時よりも悲しく、怒りが渦を巻いていたけれど耐えなければなりません。生き残るために。
私は決心しました。こんな所ではもう働けない。居るべきではないと。李春成と長い時間をかけて、練り上げた脱出計画を実行に移すことにしました。
一四人の同僚と5月4日夜一二時少し前に、稜線が海に切り立った断崖の森の中で落ち合うことにして、四、五人ずつを一組としました。李春成の組が先発し、後から行く組は集合地ちかくに着いたら小石を投げ、合図をすることも申し合わせました。
この脱出計画はうまく成功しました。もし日本兵に見付かれば、全員、金相吉や千有亀らと同じように銃殺されることは目に見えたことなので、瞬間、瞬間が息がつまりそうな緊張の連続でした。
五月五日の朝を迎えました。夜どおし前方の海上を船が走っていたのに、夜が明けると通る船はなく、遠い沖合に大きな船が停泊しているだけです。山の方も気がかりでした。いっ敗残兵がわれわれを追ってくるか心配でした。
私は、同僚たちを岩陰に残し、決死の覚悟で海辺に出て、沖の軍艦に向って手ぬぐいを振りつづけました。骨と皮だけを残した衰弱した身体なので、相手側の動きを確かめるだけの視力がありません。岩間から同僚が「きたぞ、きたぞ」と、嬉しさをかみ殺した小声でいうのですが、私の目には一向に見えません。近付いてくるランチを見た一同は小躍りして海辺に出て夢中で手を振ったのですが、三○○メートルくらい先で船首を返して停船し、乗っている兵隊たちがせわしげに動き回り、われわれ叫を観察しているだけできてくれません。みな、全身で早くきて欲しいと訴え、

